神奈川県の“三女との散策”エピソード
- misonopia aichi
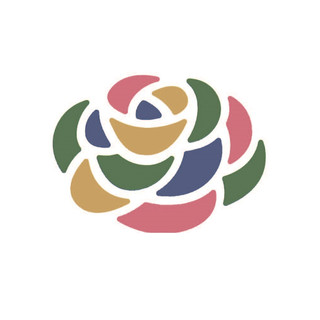
- 2023年4月10日
- 読了時間: 2分
ご入居者様 ご家族様
先月、新潟県の“長女との会食”エピソードを書かせていただきました。
今月は、神奈川県の“三女との散策”エピソードについて少し書かせていただきます。
少し前の話なのですが・・・犬を飼い始めたある日、三女と一緒に散歩をしていたとき、前方の横断歩道から歩道に渡ろうとしている歩行器を利用している高齢者の方がいらっしゃいました。
僕は“普通に見る光景”ではありました。しかし、三女にとっては、“普段目にする光景”ではないのでしょう。
突然「ガタンッ」と音がすると・・・段差がある歩道に乗り上がろうとする歩行器の高齢者の後ろに駆け寄った三女。その瞬間、よろめく歩行器の高齢者の後ろに立ち支える三女がいました。
僕は、犬の綱をもって茫然とこの光景をみていました。
再び安定して歩きはじめた歩行器の高齢者の背中を見送り、犬と僕のもとに無言でもどってくる三女。
「父親の仕事」をどこまで理解しているのかは、聞いたことはありませんが、父親としては、少し誇らしく思えました。そんな三女も、この春中学校を卒業しました。
それから間もなくして“親ばか”ですが・・・このエピソードを思い出しながら『器量』を辞書にて調べました。
【器量】
1,あることをするのにふさわしい能力や人徳
2,その人の才能に対して世間が与える評価
3,顔だち、容貌
4,もののじょうず。名人
意味合いとして、“人にはそれぞれの器の大きさがある”とのこと。
→この器量というのは、人生の中で起こる出来事に対しどれだけ許容できるのかという物事を受け入れる能力、才能の広さということ。
同じ出来事が起きた時、柔軟に対応できる人もいれば、融通が利かない人もいるとのこと。
多くの人は、大抵、器量が大きい人に惹かれ、器量が大きい人ほど他人からの信頼度も上がっていくものとのこと。
三年前の春 “コロナウィルス感染”が発症しながらの入学式。
そして、この春 卒業式で我慢せず思いっきり泣いていた三女。
日々の
“授業のあり方”“給食の食べ方”“友達との付き合い方”から、“季節行事の中止”、並びに“行事の縮小化”の
この三年間の学園生活は、“感染対策”に我慢した日々の連続だったことでしょう。
新しい人生を歩んでいくのにあたって、この我慢の体験を活かして“器量を磨く”ことに日々努力していくことを願っています。
2023年4月10日 廣井 健吉










まさに「この親にしてこの子あり」素晴らしい♪♪♪ 将来が楽しみですね。(*^_^*)