ミソノピアの風に漂いながら
- misonopia aichi
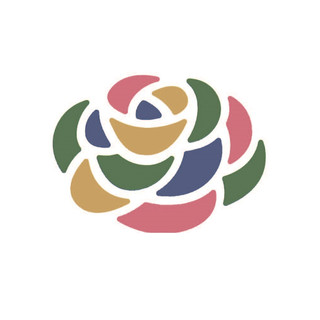
- 2023年3月31日
- 読了時間: 3分
更新日:2023年4月1日

エッセイ
「ザリガニの符号」
kaminn
私は外国の小説はほとんど読まない。翻訳者によっては文章が変な日本語になったり、登場人物のカタカナの名前が憶えられないことが理由である。
ところがどうしたことか、妙に気になっていた外国の小説を読みはじめた。
「ザリガニの鳴くところ」
この本はアメリカで大ヒット・最も売れた本ということで話題になっていた。しかし511頁の長編だ。日本の小説でさえ、このような長編には手を出したことはない自分がどうして・・・ま、数頁で投げ出してしまうだろうと頁を繰りはじめた。

小説の物語そのものに大きな起伏はないものの、ひとりの少女の成長過程の暮らしや舞台になった土地の風景や環境と差別の問題、そこに棲む生き物たちの描写、なによりも作者の見事な語り口に引き込まれて最後まで読み通してしまった。
「ザリガニ」には忘れられない想い出がある。
私がまだ20歳過ぎのころだったか、姉が就職をしていた宿舎にはじめて訪れた。宿舎のすぐ前に小川があった。なにげなく見下ろすと何匹ものザリガニが蠢いていた。幼い男の子が網で掬おうとしていたが、うまく捕れずあきらめて帰っていった。その日から、ザリガニを見るたびに想い出すのが姉のことだった。
「ザリガニの鳴くところ」を読んでいたある日のこと、私のケイタイ電話が鳴った。
姉の様子がおかしい、新聞が何日も溜まっている。近所の人からだった。すぐ駆けつけるには遠くて時間がかかるので、警察に裏のガラス窓を割って入ってもらった。
姉は倒れていて息がなかった。
これは拙著「青島(ちんとう)の砂」に書いたが、二人姉弟に育った弟の私は5歳年上で男勝りの姉に、小さいころは子分のようについてまわっていた。
気丈な姉は高齢になっても、施設入居をすすめになかなか首を縦にふらなかった。
その姉に私はずいぶん心配をかけてきた。
幼少期を育ち過ごした姉の想い出の地、中国の青島に半世紀以上を経て、私は姉をつれて行った。姉はどれほどか懐かしく嬉しかったであろう。それが私の最初にして最後の姉孝行でもあったのだ。
あれは20年ほど前のある日のこと、姉は万が一のときのために、大切なものを隠している秘密の場所を私に教えてくれたことがあった。
あの日、死を予感した姉は、私が忘れているかも知れないと思ったにちがいない。秘密の場所を私に知らせようとして、最期の力をふり絞り秘密の場所へたどり着き息絶えたのだ。
「ザリガニが鳴くところ」という本に大きな起伏はないと冒頭に記したが、物語は思いも寄らぬ結末と動きだす。
姉との想い出が「ザリガニ」であり、「ザリガニの鳴くところ」という本をなぜか読みはじめたこと、本を読み終えようとしたとき姉の訃報が入り、小説「ザリガニの鳴くところ」のクライマックスに書かれていた秘密の場所と姉が私に教えていた秘密の場所の仕様(合板の床の上げ蓋)がそっくりだったこと。
偶然にしては出来すぎているのではないか。
たとえていうなら、人知の及ばぬはたらき、それはなにかの符号であったのか・・・。
ザリガニは鳴かない。
ザリガニの鳴く【ところ】とは、本にこう書いてあった。
「茂みの奥深く、生き物たちが自然のままの姿で生きている場所」
そこは楽園。姉は「ザリガニの鳴くところ」へ向かったにちがいない。





コメント